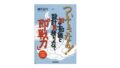基本データ
- タイトル/著者:『引き算の美学』/黛まどか
- 初版発行/出版社: 2012年2月 /毎日新聞社
感想
この本を手に取ったとき、私は「現代は物にあふれ、日本の良さが失われている」といった批判的な内容が並んでいるのではないかと思っていました。
けれども、実際にはそうした記述はごくわずかで、むしろ俳句に焦点を当てた内容が、静かに、丁寧に綴られていました。
多くのページが語っているのは、
日本人が困難な状況でも俳句を詠み続けてきたこと。
その俳句に、自然との繊細な関わりが映し出されていること。
そしてそれが、外国人には簡単に理解できない、特別な感覚であるということです。
筆者は、そうしたテーマを事細かに説明するわけではありません。
ときに自身の体験を控えめに添えるだけで、
松尾芭蕉や小林一茶、フランスの俳人、一般の方々の歌や俳句が、淡々と紹介されていきます。
しかし、不思議なことに、それらの歌や俳句を読み進めるうちに、
「引き算」の大切さや、
私たちがその「引き算の仕方」をいつの間にか忘れてしまっているという事実が、
静かに浮かび上がってくるのです。
この読書体験の中で、私はある漫画の一場面を思い出しました。
競技かるたを描いた末次由紀さんの『ちはやふる』の中に、こんなニュアンスのセリフがあります。
「先輩は飴玉のように百人一首を渡してくるが、意味は説明してくれない」
言葉で説明するより、歌そのものが伝えてくるものがある。
黛まどかさんの文章にも、まさにその感覚がありました。
俳句を通して語られる「引き算の美学」は、
理屈ではなく、余白の中にそっと置かれた言葉によって、
読む人の心にじんわりと染み込んでいくのです。
印象に残ったこと①:型があるからこそ、自由になれる
俳句には「有季定型」という型があります。
5・7・5の音数、季語、切字など、日本語ならではの決まりごとです。
これを海外に広めようとしたとき、筆者は多くの反論に直面したそうです。
言語や季節感が異なるため、型の意義が伝わりにくかったのだと思います。
それでも筆者は、「型がなければ俳句はただのショート・ポエムになる」と語ります。
なぜそこまで、型に拘るのか?
体操競技の床運動の例えが印象的でした。
床運動は、12メートル四方の枠の中で演技を行います。
選手たちは、その限られた空間をぎりぎりまで使い切ろうとします。
だからこそ、演技には緊張感が生まれます。
そして、その緊張を乗り越えて技が決まった瞬間、技は際立ち、空間が一気に華やぎます。
もし枠がなければ、ここまでの感動は生まれないでしょう。
だからこそ、筆者は俳句の「型」にこだわるのです。
この考え方は、日常生活にも通じるものがあると感じました。
最近は、制約のないことが好まれる傾向があります。
たとえば、食べ放題やデータ容量の無制限などです。
確かに、自由であることには魅力があります。
けれどもその分、一皿一皿を丁寧に味わうことが減ってしまったり、
何気なく流れてくる動画に、気づけば長い時間を費やしてしまったり——
そんなことはないでしょうか。
逆に制限があるからこそ、
自分が本当に食べたいものや見たいものは何か考えたり、
その美味しさや楽しさに感動したりすることもあるのではないでしょうか。
制約や型があるからこそ、私たちは気づけることがあります。
限られた中でこそ見えてくる、豊かさや美しさがある。
そのことを、改めて実感しました。
印象に残ったこと②:余白の力
パリで出会った華道家の言葉が紹介されていました。
「私は花を生ける時に、花は見ていません」
彼女が見ているのは、花によって生まれる“余白”なのだそうです。
花を生けているのに花を見ない——その逆説的な行いに、思わず驚かされました。
確かに、小説や映画でも、読者の想像力を引き出すために、あえて曖昧に描くことがあると聞いたことがあります。
また、アイディアが浮かぶのは、トイレやお風呂、ぼんやりしている時が多いとも言われます。
つまり、何もしていない“余白”の時間です。
私は、日常や仕事の中で、常に何かを生産していないと落ち着かず、
休日を無為に過ごすと、どこか後悔してしまうことがあります。
けれども、実はその“無駄”に見える時間、余白の中にこそ、豊かさがあるのかもしれません。
筆者は俳句について、こう語っています。
「言葉の豊穣ではなく、余白の豊穣が求められる」
情報や物にあふれる今だからこそ、意識的に余白を持つこと。
その大切さを、改めて感じました。
印象に残ったこと③:日常に潜む感動
本を読み進めるうちに、筆者の感受性に深く心を動かされました。
いくつか、特に印象に残った記述をご紹介したいと思います。
まずひとつ目は、紅葉に関する記述です。
「紅葉では、初紅葉・薄紅葉・照紅葉、紅葉明り・夕紅葉・谷紅葉・散紅葉・冬紅葉…等々…(略)…散る紅葉までめでる。ちなみに薄紅葉はわずかに始まった紅葉を指す」
「紅葉」ひとつをとっても、これほど多くの美しい言葉があることに驚きました。
特に「薄紅葉」という言葉には、衝撃を受けました。
これまで私は、紅葉狩りに出かけて、葉が染まり切っていないとがっかりしていました。
けれども、この言葉を知っていたら、一部だけ色づいた葉にも、心からめでる気持ちが湧いていたかもしれません。
俳句が人生を豊かにするとは、こういうことなのだと実感しました。
ふたつ目は、和菓子についての記述です。
「和菓子はただの甘いもの、おやつではなく、日本の伝統的な風習や行事、四季折々の花鳥風月を見事に移した総合芸術だからだ」
これも目からうろこでした。
私にとって和菓子は、“緑茶に合う、少し高価なおやつ”という印象でした。
あくまで食べ物としてしか見ていなかったのです。
しかし、和菓子は芸術であり、その見た目や名前にまで趣向が凝らされていると知り、見方が大きく変わりました。
これからはきっと、ひとつひとつの形に、名前に、込められた思いを感じながら味わうことができると思います。
そして最後に、万葉集の歌を通して語られていた、ユーモアの力についてです。
万葉集の中には、大変な暮らしの中で、苦しみや悲しみをユーモアに替えて詠んだ歌がいくつもあります。
筆者は、彼らの力強い生き様を称賛し、次のような言葉も残しています。
「笑いは成熟の証でもある」
この言葉には、深い納得がありました。
心が豊かである人ほど、自然と冗談を交えて話す——そんな姿が、静かに思い浮かびました。
この本には、はっとさせられる言葉や、考えさせられる視点が随所に詰まっていました。
何より、引用された俳句や歌が、私の言葉以上に、まっすぐ心に届いてきます。
今の生き方に少し迷いがある方にこそ、静かに手渡したい一冊です。
総評:こんな人におすすめ
- 忙しさの中で、余白や静けさを忘れかけている人
→俳句や和の美意識が、空白の時間の意味を教えてくれます。 - 型やルールに窮屈さを感じてきた人
→「型があるからこそ自由になれる」という視点に、新しい発見があります。 - 日本文化や言葉の繊細さに興味がある人
→紅葉や和菓子、季語など、日常の中の美しさに目を向けるきっかけになります。 - 感性を磨きたい、もっと深く物事を味わいたいと思っている人
→俳句を通して、見る・感じる・味わう力が育まれます。 - 創作や表現活動をしている人
→「言葉の豊穣ではなく、余白の豊穣」という考え方が、表現の幅を広げてくれます。 - 人生の意味や豊かさについて、静かに考えたい人
→華道、茶道、俳句などの文化を通して、暮らしの哲学に触れられます。