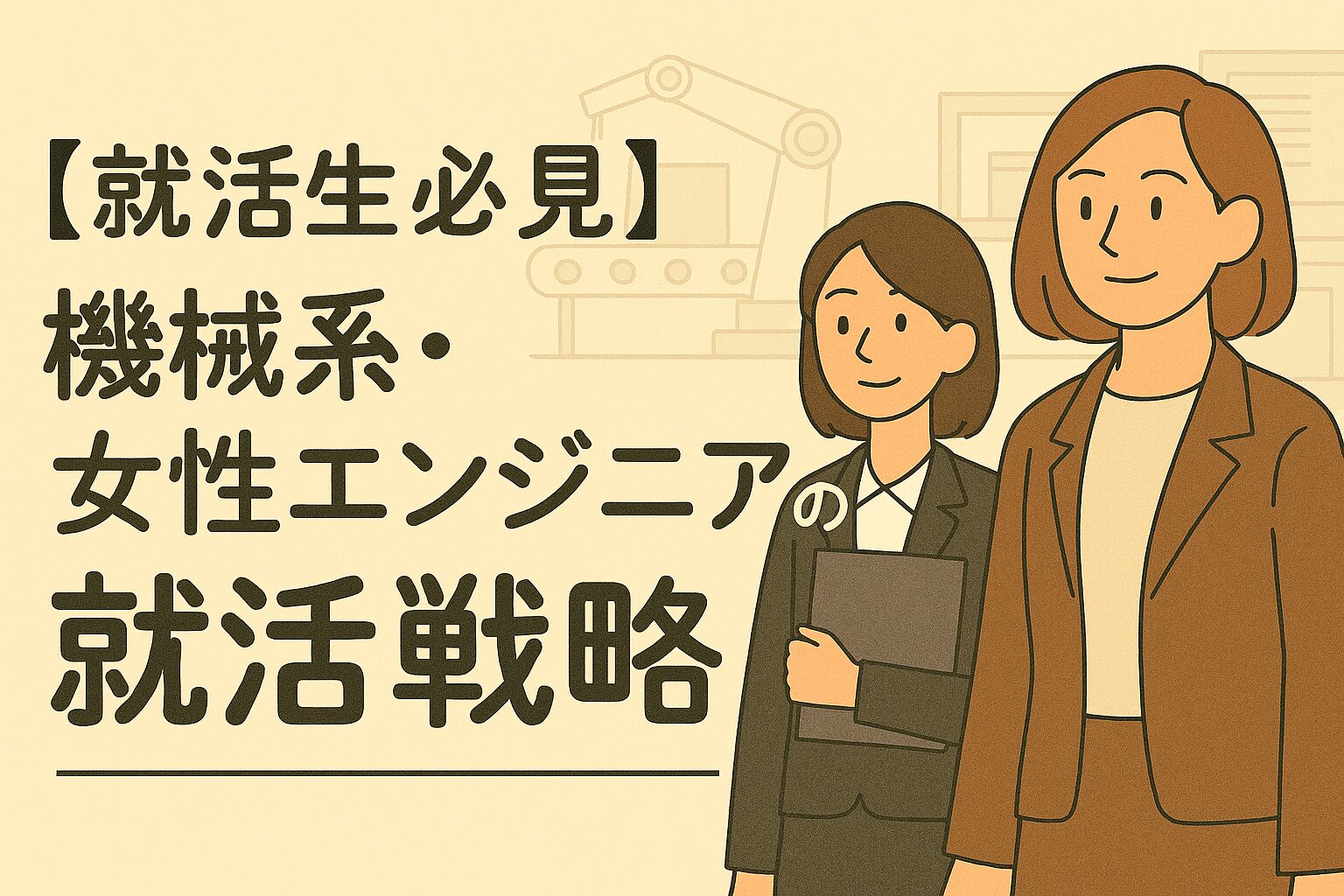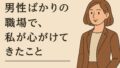こんな疑問にお答えします!
- 機械系エンジニアになりたいけど、就活では何を重視すればよい?
- 女性エンジニアが就活で気にするべき点は?
結論
- 専門より「最初の職種・業界」がキャリアの土台になる
→専門が違っても活躍できるけど、1社目の選択がその後の道を広げる鍵 - 仕事内容だけじゃなく「職場の雰囲気」もチェック
→ 空気が合うかどうかで、働きやすさや満足度が大きく変わる。 - 人事の印象と現場のリアルは別物
→ 明るい人事に惹かれて入社しても、配属先が全然違う雰囲気…なんてことも。現場の空気は自分で感じておくのが安心。 - 女性エンジニアの環境や制度も将来の安心材料に
→ ロールモデルの有無や制度の使いやすさは、長く働くうえで意外と大事。今はピンとこなくても、未来の自分のために確認しておこう。
1.学生の頃の専門はそこまで気にしなくてOK。ただし1社目の職種と業界は大事
私は学生時代、流体力学を専攻していました。
そして就職先も、コア技術が流体制御の会社。
「これは専門が活かせるかも」と思っていたのですが——実際に働いてみると、そんな機会はほとんどありませんでした。
そもそも、学問で扱う理論は、理想状態を前提にしたものが多く、現実の設計業務とはかなり違います。
現場では、外乱やコスト、納期など、いろんな制約がつきもの。
研究職ならまだしも、モノづくりの現場では、たとえ専門に近い製品を扱っていても、結局は勉強し直しなんですよね。
だから、学生時代の専門はそこまで気にしなくて大丈夫です。
実際、私の周りにも化学や生物系出身で機械系エンジニアとして活躍している人がたくさんいます。
機械専攻の人と比べても、まったく遜色ありません。
一方で、最初に選ぶ職種や業界は、その後のキャリアにけっこう影響します。
私も転職を考えたとき、まったく違う業種や業界にチャレンジしようとしたのですが、想像以上にハードルが高くて驚きました。
というのも、異業種に移ろうとすると、どうしても専門性が低く、言ってしまえば「誰でも参入できる職種」に寄ってしまう傾向があるんです。
もちろん、それが悪いわけではないのですが、これまで積み上げてきた技術や経験が活かしづらくなるのは事実です。
最終的に私は、前職と同じ業種・業界に転職しました。
そのおかげで、これまでの知識や経験をすぐに活かすことができて、新しい職場にもスムーズに馴染むことができました。
そして、長く同じ分野で働いてきたからこそ、自分の武器になったスキルや視点があると感じています。
まとめると、学生時代の専門はあまり気にしなくてOK。
でも、最初に選ぶ職種や業界は、後々の選択肢や転職のしやすさに関わってくるので、そこは少し意識しておくといいかもしれません。
2.同じ仕事でも、こんなに違う?職場の“空気”って大事です
職場の雰囲気って、想像以上に違いが出るものだなと感じています。
私は転職前後で職種は同じですが、今の方が雰囲気が合っていて、毎日がかなり快適です。
前職では、常に仕事に追われていて、ミスをすると若手でも責任を負わされるような空気がありました。
意見は通りづらく、チーム全体がピリピリしていて、食欲が落ちたり、眠れなくなることも…。
正直、精神的にかなりしんどかったです。
一方で今の職場は、業務の調整も細かくしてくれるし、意見もちゃんと聞いてもらえる。
チームのメンバーも本当に優しくて、仕事内容は大きく変わっていないのに、働きやすさが全然違うんです。
「雰囲気が合う」って、こんなに大事なんだなと実感しました。
では、どうやってその“雰囲気”が自分に合っているかを見極めればいいのか。
正直、入ってみないと分からない部分も多いです。
なので、可能であれば、実際にその職場で働いている人にプライベートで話を聞くのが一番確実だと思います。
とはいえ、そんな機会はなかなかないと思うので、私が思う「最低限ここは見ておきたいポイント」を挙げてみます。
✅1. 離職率
離職率が高い職場は、働きづらいと感じる人が多い可能性があります。
社員が定着しないと業務もひっ迫しがちなので、職場の空気が荒れているサインかもしれません。
できれば会社全体ではなく、自分が入りたい部署やチームの離職率を確認するのがおすすめです。
会社全体の数字には、雰囲気の違う部署も含まれているので、実際に配属されたときにギャップがあるかもしれません。
✅ 2. 残業時間・休暇取得率
これも、なるべく自分が入る予定の部署やチーム単位で聞いてみてください。
全社平均だと、部署ごとの差が大きくて参考にならないこともあります。
「残業が多いのは仕方ない」と思っていても、休みが取りづらい職場は地味にストレスになります。
✅ 3. チームの規模(管理職1人に対しての人数)
管理職1人に対してメンバーが多すぎると、管理が行き届かず、個人に負担が偏ることがあります。
目安としては、1人の管理職に対して4〜5人くらいが理想。
それ以上だと、役職以上の業務や責任を求められる可能性があるので、注意が必要です。
このあたりを押さえておけば、「大多数がしんどいと感じる職場」には当たりにくいと思います。
もちろん、ワークライフバランスや仕事への価値観は人それぞれなので、あくまで参考として見てもらえたら嬉しいです。
3.人事と現場の雰囲気は別物
正直、これは転職前も転職後もずっと思っていたことなんですが——
説明会や面接で会う人事の方って、会社の“顔”なんですよね。
人事の方が明るくて優しいと、「この会社、雰囲気良さそう!」って思いがちなんですが、
実際に配属される部署の空気が同じとは限りません。ここ、けっこう落とし穴です。
私も1社目は、人事の方の明るさに惹かれて入社したんですが、
いざ配属されると、設計の現場はかなりドライでびっくりしました。
「えっ、あの笑顔はどこへ…?」って感じでした(笑)
2社目は比較的ギャップが少なかったんですが、
入社後に人事部の方が「設計部署って、ちょっと人事とは雰囲気違うよね〜」とさらっと言っていて、
「やっぱりそうなんだ…!」と内心ツッコミました。
なので、会社の雰囲気=人事の雰囲気と思い込むのは危険です。
できれば、実際にその部署で働いている人にプライベートで話を聞くのが一番確実。
それが難しい場合でも、OB・OG訪問やインターンで現場の空気を直に感じるのが安心です。
4.女性エンジニアとして働くなら、制度だけじゃない。“前例”がある職場は話しやすい
社会人になってから、女性で機械系エンジニアのロールモデルが本当に少ないことに驚きました。
学生の頃は、キャリアパスを描いたり、将来を気にしたりしない人も多いと思います。
でも、いつかきっと「自分はどうなりたいか」を考えるタイミングが来るはずです。
そんなとき、複数のロールモデルがいるとすごく助かるんですよね。
職場も、女性がエンジニアとして働くことに慣れていれば、制度や雰囲気も整っていて、自然と相談しやすくなります。
私の前職には、女性エンジニアが2名いました。
ただ、正直なところ、職場全体が女性エンジニアに慣れていない空気だったと思います。
片方の方は地方の支部で自由に働いていたのですが、時々その自由さが周囲の反感を買っている様子もありました。
もう片方の方は、子育てをしながら管理職をされていましたが、早く帰ることでメンバーから疎まれているように見えました。
職場としても、女性エンジニアの受け入れ態勢が整っていなかったと思います。
そもそも人数が少ないので、ロールモデルもいないし、子育てや昇進の実績もほとんどない。
あのまま前の職場で働き続けていたら、出産や出世に関係なく、自分のポジションを確保するには一から切り開くしかなくて、かなり苦労していたと思います。
今の職場には、女性の管理職も多く、育休や産休を取っている方もいます。
そういう実績があるだけで、「自分にもその道があるんだ」と思えるし、上司にも自然と話しやすくなります。
だからこそ、女性管理職がいるか、育休やフレックスが使いやすいかは、長く働く上で本当に大事なポイント。
就活のときはピンとこないかもしれませんが、将来の自分を想像して、確認しておくと安心です。
最後に
実際に働いてみたり、キャリアについて考えるようになってから、
「学生の頃にはなかった視点」がいろいろ見えてきました。
あの頃の私は、そんなこと考えもしなかったなぁ…と今になって思います。
だからこそ、今回はその気づきをまとめてみました。
少しでも、これから就活をする方や、キャリアに悩んでいる方の参考になったら嬉しいです。
私自身も、まだまだ道の途中。
失敗もたくさんしながら、試行錯誤して進んでいる最中です。
これからも、そんな日々の中で気づいたことや学んだことを、
この場所で少しずつ、ゆるやかに共有していけたらと思っています。