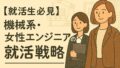こんな疑問にお答えします!
- 大学で学んだことって、現場でどこまで役に立つの?
- 設計って、CADで形を作るだけじゃないの?
大学では、理論式を覚えたり、実験したり、計算したり。
もちろんそれも大切ですが、実際にエンジニアとして働いてみると、「あれ?これって習ってないぞ…?」という場面が山ほど出てきます。
ここでは、私が現場で痛感した「大学ではほぼ習わないけど、めちゃくちゃ使う知識」を5つご紹介します。
結論
- 規格:設計の前提となる「技術の共通言語」。知らないと製品が売れないことも。
- 公差:寸法のばらつきを考慮しないと、量産で「組めない」トラブルが起きる。
- 製造方法:CADで描けても、実際に作れるとは限らない。加工のリアルを知るべし。
- 検査方法:測れない寸法は意味がない。検査できる構造にするのが設計者の責任。
- コスト:技術だけでなく「いくらで作れるか」も設計の大事な視点。
1. 規格:業界のお作法を知らずに設計はできない
規格には大きく分けて二つの側面があります。
ひとつは「お作法」としての規格です。
JISのように業界内で共通の基準を持つことで、設計や製造のやり取りがスムーズになります。
法律で強制されていない場合も多く、守らなくても罰則はありません。
ただし、JISから外れた設計だとメーカーが対応できなかったり、コストが跳ね上がったりするため、実務上は守ったほうが確実に有利です。
もうひとつは「守らなければならない規格」。
CEマーク(EU)、FCC(米国)、技適マーク(日本の通信機器)、PSEマーク(日本の電気製品)などが代表例です。
これらは法律や指令と結びついており、適合していなければ販売すらできません。
つまり、規格は単なるマナーであると同時に、市場に入るための入場券でもあるのです。
私自身、入社当初は「JISって聞いたことあるな…」程度の認識で、正直ほとんど理解していませんでした。
しかし実際に働き始めると、何かと規格を調べて設計していました。
なぜなら、規格を守らなければ製造できなかったり、そもそも製品を売ることができなかったりするからです。
2. 公差:図面の「10mm」は10mmじゃない
公差とは、製品の寸法に許される誤差の範囲のことです。
図面に「10mm」と書いてあっても、実際には±0.1mmといったばらつきが必ず生じます。
このばらつきを考慮せずに設計すると、試作では組み立てられても、量産では「組めない…」という悲劇が起こります。
なぜなら、数が増えるほどばらつきも大きくなるからです。
私が設計を始めた当初は、公差を「精度が必要なところを加工精度に合わせて設定する程度」と考えていました。
しかし本当に大切なのは、設計段階から「この製品が組み立つには、あるいは性能を発揮するには、どこまでズレても大丈夫か?」を意識することです。
その結果、算出した公差が実際の加工精度より厳しいなら、構造そのものを見直さなければなりません。
会社によってはKKD(勘・経験・度胸)で公差を決めているところもありますが、最近は「KKDに頼りすぎるのは危険」と言われています。
属人的で再現性が低いからです。
公差設計にはいくつかの手法があり、学びながら自分なりの最適解を見つけていくことが大切です。(私自身もまだ道半ばです…)
それが、量産で泣かないための第一歩になります。
3. 製造方法:CADで描けても、作れなきゃ意味がない
製造方法とは、部品を実際にどうやって作るかという技術のこと。
切削、鋳造、プレス、樹脂成形など、方法によってできる形状や精度が違います。
最近は3D CADで自由に形を描けますが、「これ、どうやって作るの?」と聞かれて固まった経験、何度もあります。
例えば、切削では刃物が入らない形状は作れませんし、ピン角(90度の角)も加工できない場合があり
また、加工精度も重要なポイントです。
ばらつきを考慮した結果、「ここは0.001mmの精度が必要」と図面に指示したとしても、実際にはその精度での加工が不可能な場合も少なくありません。
設計の大前提は「実際に作れること」です。
CADではどんな形でも描けますが、その自由さに惑わされてはいけません。
大切なのは、製造現場のリアルを思い描きながら、現実に落とし込める設計をする力です。
4. 検査方法:測れない寸法は、意味がない
検査方法とは、製品が設計通りにできているかを確認する手段のことです。
工程内検査や出荷前検査など、品質を担保するために欠かせません。
図面に「形状を確定させるため」と何も考えず寸法を入れていませんか?
その寸法、本当に測れるでしょうか。
私も入社当初は「測れるか分からないけど、製造側がなんとかしてくれるだろう」と思っていました。しかし実際には、それは設計者の責任です。
検査できない寸法を指示するのではなく、代替となる箇所に寸法を入れる、あるいは検査可能な基準面を設けるなどの工夫が必要です。
さらに、サプライヤーがどんな計測機を持っているのか、特殊な装置がなければ測定できない仕様になっていないかも考慮しなければなりません。
設計段階ではつい後回しにしがちですが、そこまで想定しておくことが、最終的に品質の高い製品づくりにつながります。
5. コスト:設計は、利益とセットで考える
コストとは、製品を作るためにかかるお金のことです。
材料費、加工費、組立費、検査費など、設計の選択によって大きく変わります。
当然、製品を売る以上は利益を出さなければなりません。
そのためには、なるべく安く作る工夫が欠かせません。
加工方法や材料の高低を把握し、仕様と照らし合わせながら最適な解を導くことが求められます。
さらに、最終製品だけでなく、各プロジェクトには年間の予算が設定されています。
多くの場合はマネジメント職が管理しますが、エンジニアに対しても大まかな予算算出を求められることがあります。
また、試作で見積もりを取る際には、予測を立てたり、提示された価格が適正かどうかを判断する力も必要です。
最後に:焦らず、少しずつ蓄えていこう
これらの知識は、大学ではほとんど触れません。
私も入社してから「えっ、そんなの知らない…」と何度も戸惑いました。
しかも、これらはノウハウの塊。
ネットや教科書だけでは限界があります。
だからこそ、現場で少しずつ経験しながら、自分の中に蓄えていくことが大切です。
焦らなくて大丈夫。
一歩ずつ、確実に身につけていきましょう。